皆さんは「ファッション」なるものを、どのようにとらえていますか? これは様々なキーワードから謎多き「ファッション」を紐解いていく連載です。
「メディア」とファッションの深いつながり
現代のファッションについて知りたければ、InstagramなどのSNSがいちばん有効であろうことは、周知の事実だと思います。日々新しいコーディネートがアップロードされ、インフルエンサーは発信を続けている……現代ではこうした媒体が、流行を伝えるメディアとして非常に重要な役割を果たしているのです。ファッション研究者のロカモラは、現代のファッションとメディアの関係性を「メディア化」という概念で説明しています。いわく、メディアは情報を伝達するためだけのものではなく、ファッションを取り巻く実践(実際にどんな服装が好まれるのか、などの流行の指標)がメディアに応じてどう変容してきたか、ということに着目する必要があり、メディア化のプロセスとその効力は、歴史的かつ包括的な視点から見ることによって明らかになる、と(Rocamora 2017 )。そういった視点でメディアとファッションの関係を考えてみるのが、今回のテーマです。
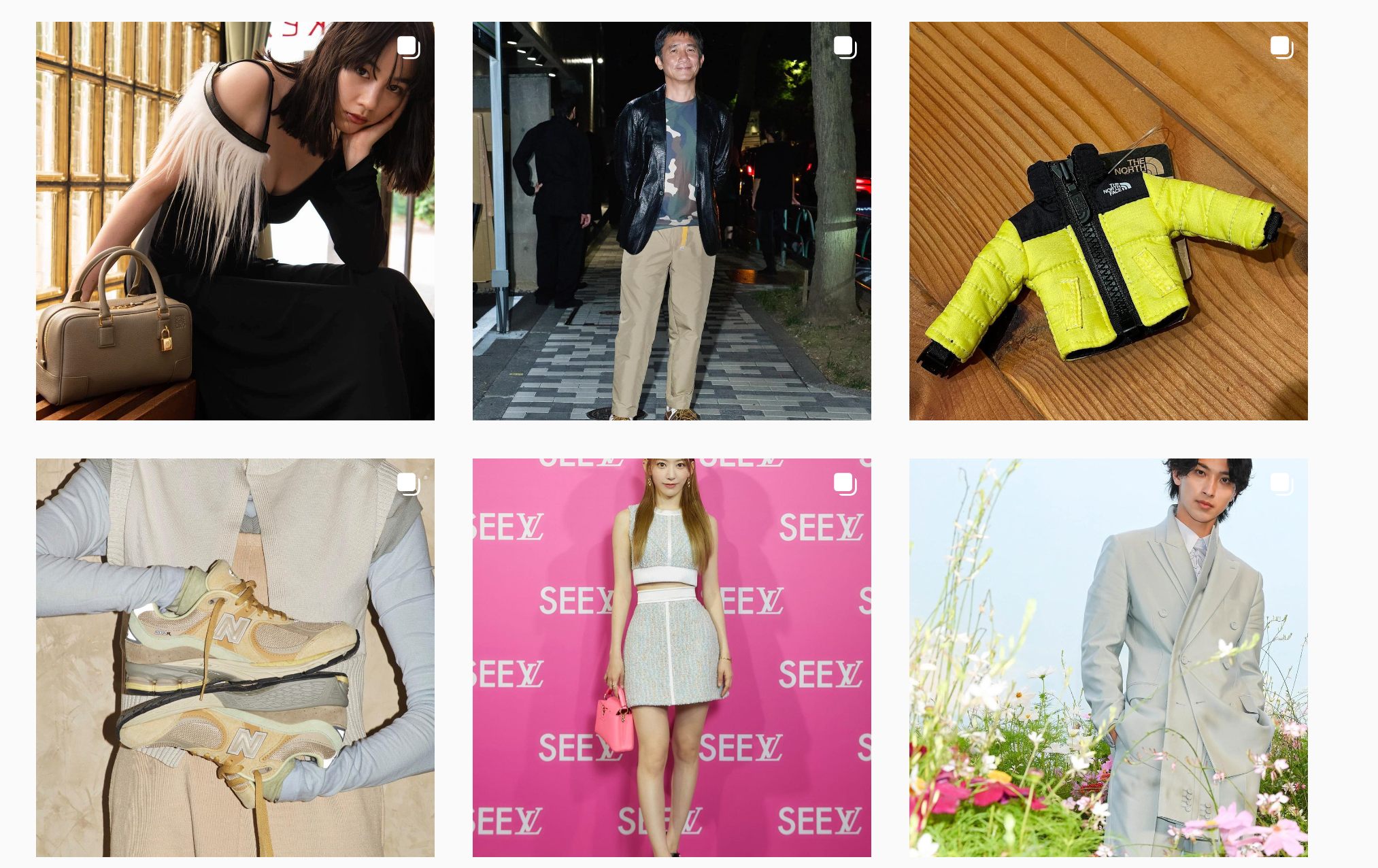
(出典:Instagram)
デジタルメディアが登場する前については、フランスの思想家ロラン・バルト(1915-1980)が『モードの体系』という書籍で研究したものが有名です。このときの調査対象は「服」ではなく「ファッション雑誌」だったことがポイントになってきます。バルトはメディア、つまりファッション雑誌が服そのものよりも流行をつくりだすうえで決定的な役割を果たすと見抜いていたのです。バルトによれば、「欲望を起こさせるものは対象[物]そのものではなくて名前であり、人に物を売るのは夢ではなく意味のしわざ」なのだそうです。誰でも、有名人の持っている服飾品が欲しくなることがあるはずです。あるいは、今話題になっている服飾品も欲しくなると思います。それをバルトは特定の年代のファッション誌を選んで記載されている用語を抽出し、「言葉」でどのように表現され、流行を生む機能があったのかを分析しました。つまり我々の欲望を喚起するのは、ファッション誌などによって記号となった「服にまつわる言葉」なのです。バルトは「言葉」によって流行が作り出されることを指摘しましたが、決してイメージの優位性を否定したわけではありません。言葉がイメージをいかに指示し、強調し、確定するのかを分析した、というわけです。
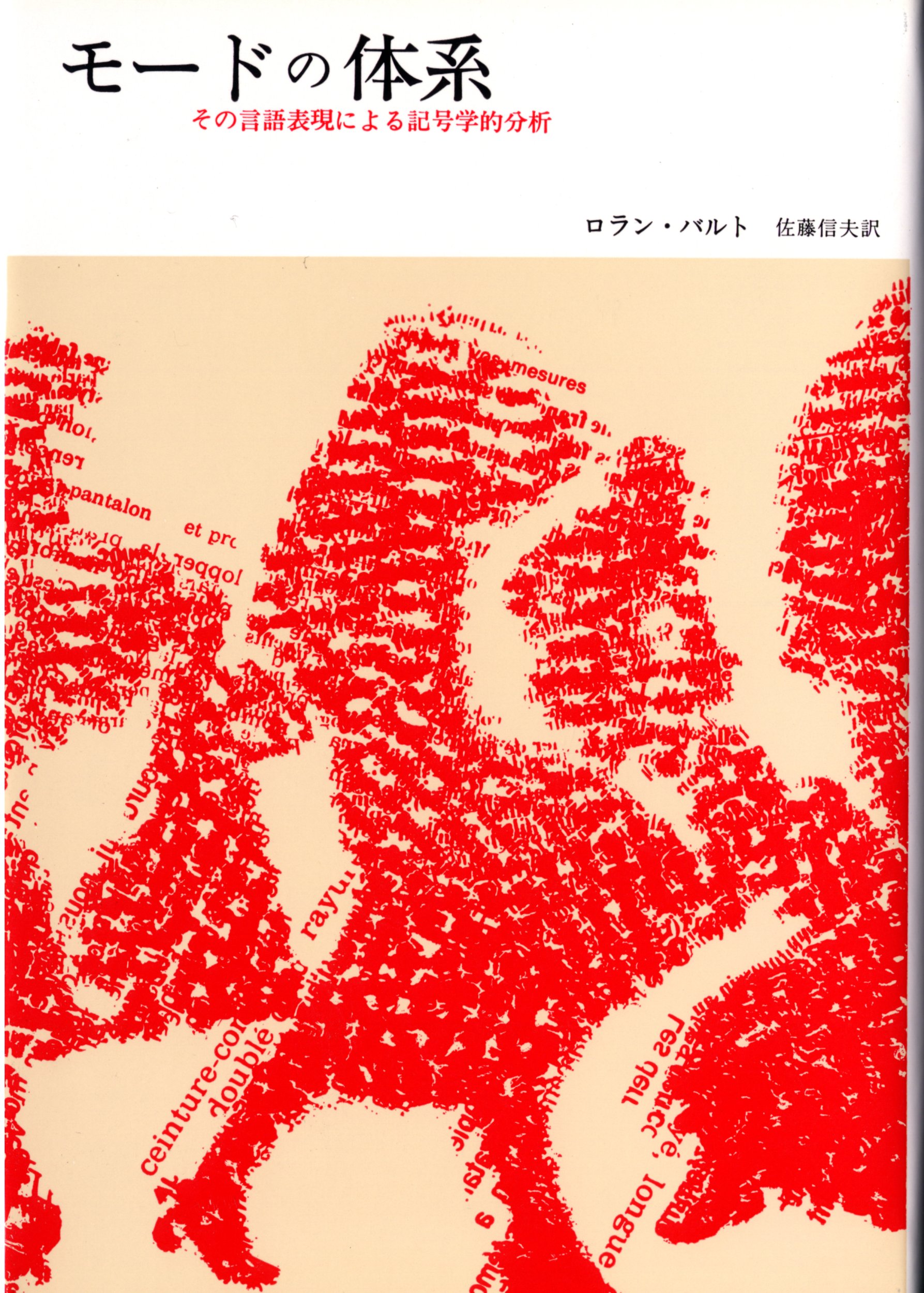
(出典:Amazon.com)
では、ファッション誌が生まれる以前には他人の服装が気にならなかったのか? と考えてしまうのですが、実際はそうでもないのです。15~17世紀にかけての大航海時代にアフリカやアメリカ大陸を航海したヨーロッパの探検家たちが持ち帰った土産話が知られるようになって、人々は異国の服装に興味を示しました。そして見知らぬ土地の服飾の版画集なども出版されるようになり、イメージや言葉で現地の服飾を伝え、関心を寄せる人々も多かったそうです。
ファッション雑誌は、「ファッション」が情報としての価値を持つようになったからこそ成立する。そう考えた方がよりよく理解できる現象が、ちょうどルイ14世の絶対王政期のフランスで起こりました。この頃フランスでは服飾産業が発展しましたが、宮廷での流行情報を伝えた雑誌が発行されましたし、その後19世紀にもファッションを専門的に取り上げる雑誌が刊行されました。初期のファッション雑誌には流行のスタイル、生地、装飾、色彩などを詳しく報じる絵(ファッションプレート)が挿入されていました。そして流行の発信地であるパリのことを海外に報じる雑誌が登場し、その影響力はさらに増していきます。ヴォーグなどはアメリカのファッション雑誌ですが、これらは同時代にパリで誕生したオートクチュールのファッションを取り上げて世界に伝えて人気になった、という背景があります。では、雑誌が伝えた流行の情報はどのように利用されたのでしょう。
19世紀後半には、パリにオートクチュール店を開いたデザイナーが新しいスタイリングを季節ごとに発表するようになります。それを、「雑誌で見たこれを作ってください!」とアメリカに住んでいる人も、地元のお店に言ってパリで流行している服を着られるようになったのです。また、型紙付きの雑誌も登場し、型紙を使って自分で縫う人もいました。ただ、その型紙は使い古されたら捨てられてしまうもので、流行の伝達をする重要な役割を果たしても消えてしまうメディアでした。
(出典:Amazon.com)
私はこう見る!
TikTokやTwitterあるいはInstagramなど、我々は生活の中でメディアにたくさん触れています。そういったアプリを使わなくても、テレビや新聞、雑誌もメディアです。だから私たちの暮らしにメディアが占める割合は相当高いのです。そのメディアとの付き合い方も、少しずつ変えていかなければならないのかもしれないな、とも私は考えています。
自分自身がメディアに振り回されて、結局自分のしたいこと、目指しているスタイルって何だろう、と迷うことが多くなったと感じていて、そういうメディアと距離を取りたいけれど、メディアなしではもう生活ができない。そんな人は私以外にもいると思います。そんな現状で私が実践しているのは、「鵜呑みにしない(自分の目で確かめる)」「余計な情報を入れない」ということです。
たくさんの情報の中で、実際に体験したこと、実際に見たもののほうが説得力があるのは自明の理ですね。百聞は一見に如かず、まさにその通りで自分の目で確かめた情報をもとにして、ファッションのスタイリングを決めるようにしています。だからあまりファッションのことで「思っていたのとは違う!」という事態にはならなくなりました。そして自分の目の中に入ってくる情報量を制限することもしています。意図的にメディアと距離を取る、という感じ。メディアと上手く付き合うことが現代人に必要なスキルだと思うので、皆さんもメディアと仲良くできるよう、流行り廃りに振り回されぬよう、楽しくメディアを扱ってほしいです。
ファッションについて考察していくコラム、今回はここまでです。
(参考文献:「クリティカルワード ファッションスタディーズ 私と社会と衣服の関係」2022年、フィルムアート社)
ライティング:長島諒子

